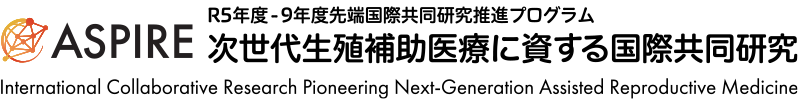2025.11.07
留学便り:古目谷博士@米国Cleveland Clinic
米国Cleveland Clinicに留学していた古目谷博士より留学便りが届きました!

AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE 2025でのラボメンバーとの写真
Cleveland Clinic 泌尿器科 Male Infertility and Men’s Health 部門での留学を終えて
私は米国オハイオ州クリーブランドにある Cleveland Clinic に留学いたしました。
Cleveland Clinicは全米でも屈指の医療・研究機関であり、2022年には全米50州および128か国から340万人以上の患者が受診しています。世界的に高い評価を受ける医療水準と研究体制を兼ね備え、基礎研究から臨床応用までが緊密に連携している点が大きな特徴です。
私が所属した泌尿器科の Male Infertility and Men’s Health 部門(Dr. Scott の Andrology Laboratory) では、男性不妊症の臨床研究、マイクロバイオーム解析、さらには精子形成の基礎研究など幅広いテーマに取り組んでいます。また、日本ではまだ限られた施設でしか行われていない、将来の妊孕性温存を目的とした小児精巣組織の凍結保存にも積極的に取り組んでおり、私もその研究の一端を担いました。日本でマウスや成人ヒト検体を用いて精子形成研究を行ってきた経験をもとに、留学中は小児ヒト検体を対象とした研究にも従事しました。
Cleveland Clinic で特に印象的であったのは、研究を支える組織的な支援体制の充実です。研究所内には Cell Culture Core、Imaging Core、Genomic Core などの専門部署があり、それぞれの分野に熟練した研究スタッフが常駐しています。初対面でも気軽に相談できる雰囲気があり、研究のアイデア段階から実現までをスムーズに進めることができました。専門家との協働を通して、研究を「個人の作業」ではなく「連携による創造」として捉える視点が得られたことは、非常に貴重な経験でした。
また、日米間でのコミュニケーションスタイルの違いも強く印象に残っています。アメリカでは、十分に資料を整えてから打ち合わせをするよりも、まず直接会って話をすることが重視されます。最初は「資料をしっかり作らずに相談するのは失礼ではないか」という日本的な戸惑いもありましたが、こちらでは、完璧な資料を作るために時間をかけるよりも、その時間を使って研究を進めることを重視している研究者が多い印象でした。この合理的でスピード感のある姿勢には大きな驚きを覚えるとともに、実際に議論を重ねることで研究が前進する実感を得ることができました。
指導者である Dr. Scott は、常に臨床医の視点をもって研究に取り組まれており、「この研究が患者さんにどのような利益をもたらすのか」という問いを常に意識されています。その姿勢は、私が日本で医師として大切にしてきた理念と一致しており、国を越えても変わらない医療者の本質を改めて感じました。「患者さんのためになる研究を行う」という共通の目的を共有できたことは、この留学で得た最も大きな喜びの一つです。
もちろん、米国での研究生活には困難もありました。物品の納期が大幅に遅れたり、手続きが途中で止まったりすることが少なくなく、そのたびに関係者と何度も確認を重ねる必要がありました。しかし、そうした経験を通じて、異なる環境下で柔軟に対応しながら研究を前に進める力を培うことができたと感じています。
この1年間を通して、異なる研究文化や思考法に触れたことで、自らの研究観が大きく広がりました。現在は、Dr. Scottとの信頼関係を基盤として、日米共同研究を継続的に発展させるための体制づくりを進めています。
今回の留学で得た経験を糧に、今後もヒト精巣の機能解明や妊孕性温存研究の発展に貢献し、将来的には不妊症治療や再生医療の分野に新たな可能性を切り拓いていきたいと考えています。
(横浜市立大学泌尿器科・古目谷 暢)